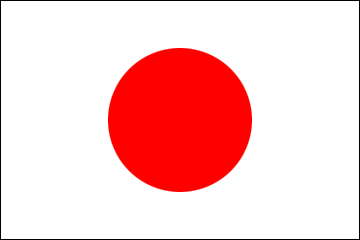セブ便り(第10回) 「マンゴー・ビジネスの成功者」
令和4年10月19日
セブ便り(第10回)「マンゴー・ビジネスの成功者」
セブには、「マンゴー・キング」と呼ばれているフィリピン人ビジネスマンがいます。名前は、ジャスティン・オイ。フィリピン最大のドライ・フルーツ加工会社「プロフード・インターナショナル」社の会長兼社長です。ドライ・フルーツ加工事業に成功した後、Jパーク・アイランド・リゾート(ホテル)やJセンター・モール(ショッピング・モール)などを買収し、それらの会長も務めています。
彼はどのようにしてマンゴー・ビジネスで成功を収めたのでしょうか。彼は、1958年に11人兄弟の4番目としてセブに生まれます。父親は、タバコの行商をしていました。彼は、12歳で、父親のビジネスを手伝い始めます。そして、家族の生活を助けるため、様々なビジネスを試みます。15歳の時から、宝石取引、養鶏(採卵)、マッシュルーム栽培などを試みましたが、資金不足などによりどれも長続きしませんでした。1978年、19歳になった時、マンゴー・ビジネスに出会います。彼は、セブでは、マンゴー収穫期(3月から5月)になると、多くのマンゴーが熟すのにもかかわらず、誰もマンゴーを買わないので、ほとんどが収穫されずに捨てられていることに気づいたのです。彼は、7名の従業員とともに、マンゴーをもらってきて、ドライ・マンゴーを作るビジネスを始めます。「プロフード・インターナショナル」社の誕生です。
ドライ・マンゴー・ビジネスは最初から順調だったわけではないようです。同業他社7社が1950年代からすでに活動していて、フィリピン国内でドライ・マンゴーを拡販することは困難でした。そこで、彼は、香港を皮切りに、ドライ・マンゴーの輸出を試みます。
ジャスティン・オイ氏によれば、事業拡大の転機は、1986年と1993年に訪れました。1986年、彼は、日本貿易振興機構(JETRO)の招待で訪日し、2週間にわたって、日本の生産施設や流通システムを視察する機会に恵まれ、日本のマーケットに食い込むためには高い品質が求められることを学びます。また、同年、オランダ政府の招待でロッテルダムを訪問し、1ヶ月にわたって、欧州の市場を調査します。
1993年、彼は、フィリピン政府の技術生活資金センター(Technology and Livelihood Resource Center, TLRC)から融資を受けることに成功し、その資金で機械を購入し、国際的な認証を得るために必要な工場の近代化に成功します。なお、このTLRCによる融資の原資は、国際協力機構(JICA)の「農業技術移転プロジェクト」という低利融資事業のもので、合計約4億円がTLRCを通じて114件の事業に貸し付けられました。融資を受けて工場を近代化した数年後には、同社は、フィリピン国内で最大のドライ・フルーツ加工企業に成長します。
現在、同社は、1日に300万切れのドライ・マンゴーを生産し、50カ国以上に輸出しています。収穫期には、セブの工場では、約6000人が働き、マニラやダバオの工場でも数百人が働いています。自社ブランドでの製品が全体の生産量の65%、「インダストリアル」と呼ばれる他企業に提供する原材料(マンゴー、パイナップル、カラマンシーその他のフルーツのピューレや加工フルーツ)生産が25%、「Toll Packing」と呼ばれる他社ブランド(デル・モンテ、ネッスル、コカコーラ等)のための生産が10%を占めるそうです。
ジャスティン・オイ氏は、セブの工場で働く人々は、概して協力的で、他の地域と比べて労働争議も少ないと言います。また、セブは、フィリピンの真ん中に位置しているので、フィリピンの各地から最適な素材を集めることができるとも言います。セブの良質な労働力や、地理的位置は、事業成功の背景を形成したのでしょう。
彼のビジネスの成功には、いくつかの要因が作用しています。早い段階から国内市場ではなく輸出に目を向けたこと、海外市場では品質管理が重要であることを認識したこと、得られた資金を機械化に回し、それによって国際認証取り付けに必要な品質管理を確保したこと等です。
しかし、私は、彼の事業成功の最も大きな要因は、彼自身の献身的努力にあると思います。事業を始めてから18年間は、1日も休まずに、毎日18時間働き続けたそうです。JETROの招聘やTLRCの融資にしても、粘り強く何度も応募を繰り返した結果だそうです。一つのことに打ち込み、粘り強く続けたことが事業成功の一番の秘訣だったのではないでしょうか。
彼はどのようにしてマンゴー・ビジネスで成功を収めたのでしょうか。彼は、1958年に11人兄弟の4番目としてセブに生まれます。父親は、タバコの行商をしていました。彼は、12歳で、父親のビジネスを手伝い始めます。そして、家族の生活を助けるため、様々なビジネスを試みます。15歳の時から、宝石取引、養鶏(採卵)、マッシュルーム栽培などを試みましたが、資金不足などによりどれも長続きしませんでした。1978年、19歳になった時、マンゴー・ビジネスに出会います。彼は、セブでは、マンゴー収穫期(3月から5月)になると、多くのマンゴーが熟すのにもかかわらず、誰もマンゴーを買わないので、ほとんどが収穫されずに捨てられていることに気づいたのです。彼は、7名の従業員とともに、マンゴーをもらってきて、ドライ・マンゴーを作るビジネスを始めます。「プロフード・インターナショナル」社の誕生です。
ドライ・マンゴー・ビジネスは最初から順調だったわけではないようです。同業他社7社が1950年代からすでに活動していて、フィリピン国内でドライ・マンゴーを拡販することは困難でした。そこで、彼は、香港を皮切りに、ドライ・マンゴーの輸出を試みます。
ジャスティン・オイ氏によれば、事業拡大の転機は、1986年と1993年に訪れました。1986年、彼は、日本貿易振興機構(JETRO)の招待で訪日し、2週間にわたって、日本の生産施設や流通システムを視察する機会に恵まれ、日本のマーケットに食い込むためには高い品質が求められることを学びます。また、同年、オランダ政府の招待でロッテルダムを訪問し、1ヶ月にわたって、欧州の市場を調査します。
1993年、彼は、フィリピン政府の技術生活資金センター(Technology and Livelihood Resource Center, TLRC)から融資を受けることに成功し、その資金で機械を購入し、国際的な認証を得るために必要な工場の近代化に成功します。なお、このTLRCによる融資の原資は、国際協力機構(JICA)の「農業技術移転プロジェクト」という低利融資事業のもので、合計約4億円がTLRCを通じて114件の事業に貸し付けられました。融資を受けて工場を近代化した数年後には、同社は、フィリピン国内で最大のドライ・フルーツ加工企業に成長します。
現在、同社は、1日に300万切れのドライ・マンゴーを生産し、50カ国以上に輸出しています。収穫期には、セブの工場では、約6000人が働き、マニラやダバオの工場でも数百人が働いています。自社ブランドでの製品が全体の生産量の65%、「インダストリアル」と呼ばれる他企業に提供する原材料(マンゴー、パイナップル、カラマンシーその他のフルーツのピューレや加工フルーツ)生産が25%、「Toll Packing」と呼ばれる他社ブランド(デル・モンテ、ネッスル、コカコーラ等)のための生産が10%を占めるそうです。
ジャスティン・オイ氏は、セブの工場で働く人々は、概して協力的で、他の地域と比べて労働争議も少ないと言います。また、セブは、フィリピンの真ん中に位置しているので、フィリピンの各地から最適な素材を集めることができるとも言います。セブの良質な労働力や、地理的位置は、事業成功の背景を形成したのでしょう。
彼のビジネスの成功には、いくつかの要因が作用しています。早い段階から国内市場ではなく輸出に目を向けたこと、海外市場では品質管理が重要であることを認識したこと、得られた資金を機械化に回し、それによって国際認証取り付けに必要な品質管理を確保したこと等です。
しかし、私は、彼の事業成功の最も大きな要因は、彼自身の献身的努力にあると思います。事業を始めてから18年間は、1日も休まずに、毎日18時間働き続けたそうです。JETROの招聘やTLRCの融資にしても、粘り強く何度も応募を繰り返した結果だそうです。一つのことに打ち込み、粘り強く続けたことが事業成功の一番の秘訣だったのではないでしょうか。
(ジャスティン・オイ氏と筆者、プロフード・インターナショナル社にて)

在セブ総領事 山地秀樹
(了)