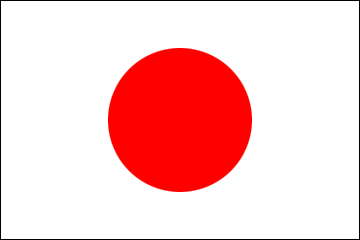セブ便り(第16回) 「フィリピンの国の構造-中央集権型なの?地方分権型なの?」
令和5年3月15日
セブ便り(第16回)「フィリピンの国の構造-中央集権型なの?地方分権型なの?」
セブに着任する前、フィリピンのことを何も知らなかった私は、「フィリピンは、長く米国の植民地だったので、州の権限が強い米国の連邦制のような構造なのかな。」と考え、フィリピンでの勤務経験がある先輩大使に、「フィリピンって、アメリカのような地方分権型の国ですか。」という質問をしたことがあります。その大使は、「そんなことも知らないのか。」という顔をされ、「フィリピンは中央集権型だよ。」とお答えになりました。私は、「そういうものか。」と自分を納得させ、これを基礎知識としてもってセブに赴任しました。なお、この会話での、「中央集権」、「地方分権」という用語は、中央政府の権限が強く、中央の統制が地方にまで行き渡っており、外交をする上で、中央政府と付き合い、その動きを見ていればほぼ事足りるのかどうかという問題意識に基づくもので、政治学及び行政学上の厳密な定義に基づくものではありません。
しかし、セブに着任して10ヶ月で見聞したことの多くは、「フィリピンは中央集権型であるはず。」との考えを揺るがせるものでした。詳しくはご説明できませんが、州や市の警察本部長の人事権、コーストガード隊員の利用、フィリピン国軍の司令部をどこに置くかについての意見表明、国が予算を出す道路や橋梁への意見表明などの点で、地方政府(州、市)の権限が、日本の常識から想像するよりもはるかに大きいことに気づきました。こういうことが重なり、私の中では、「フィリピンって本当に中央集権型の国なのか。」という疑念が膨らんでいきました。
この疑念を決定的にしたのは、私が、セブでの固形廃棄物処理の現状について調べるため、当地の環境天然資源省の関係者と意見交換をしていた時の先方の会話でした。その関係者は、「2021年に地方分権(Devolution)に関する大統領命令が出されたため、環境天然資源省第7管区の予算のうち施設や機器に関するものは、第7管区の地方政府132(16市及び116町)にそれぞれ100万ペソずつ、地方政府に直接配分されることになった。それまで1億3000万ペソ近くの予算を有していた環境天然資源省には、もはやこの分野の予算は配分されないので何もできない。一方で、予算を配分された市町の側も、100万ペソの少額では何もできないだろう。」と述べました。この発言は私にとりかなりショックでした。この指摘は、国の機能を低下させ、且つ地方政府の機能向上の助けにもならない、何か好ましくないことが起きている可能性を示唆していたからです。
しかし、セブに着任して10ヶ月で見聞したことの多くは、「フィリピンは中央集権型であるはず。」との考えを揺るがせるものでした。詳しくはご説明できませんが、州や市の警察本部長の人事権、コーストガード隊員の利用、フィリピン国軍の司令部をどこに置くかについての意見表明、国が予算を出す道路や橋梁への意見表明などの点で、地方政府(州、市)の権限が、日本の常識から想像するよりもはるかに大きいことに気づきました。こういうことが重なり、私の中では、「フィリピンって本当に中央集権型の国なのか。」という疑念が膨らんでいきました。
この疑念を決定的にしたのは、私が、セブでの固形廃棄物処理の現状について調べるため、当地の環境天然資源省の関係者と意見交換をしていた時の先方の会話でした。その関係者は、「2021年に地方分権(Devolution)に関する大統領命令が出されたため、環境天然資源省第7管区の予算のうち施設や機器に関するものは、第7管区の地方政府132(16市及び116町)にそれぞれ100万ペソずつ、地方政府に直接配分されることになった。それまで1億3000万ペソ近くの予算を有していた環境天然資源省には、もはやこの分野の予算は配分されないので何もできない。一方で、予算を配分された市町の側も、100万ペソの少額では何もできないだろう。」と述べました。この発言は私にとりかなりショックでした。この指摘は、国の機能を低下させ、且つ地方政府の機能向上の助けにもならない、何か好ましくないことが起きている可能性を示唆していたからです。
(イナヤワン廃棄物最終処分場で環境天然資源省第7管区担当者及びセブ市環境総括とともに)


その後、自分なりに調べてみてわかったことは、フィリピンでの中央集権及び地方分権をめぐっては、次のような大きな流れがあるということです。まず、前マルコス政権(1965年~1986年)の下で、特に1969年の戒厳令発布以降、国の中央集権化(大統領の権限強化を含む。)が大幅に進みます。しかし、マルコス大統領は、1986年、「エドサ革命(独裁体制の終了を求める民衆運動)」によって失脚し、米国に亡命します。代わって登場したコラソン・アキノ大統領(マルコス大統領の政敵で、暗殺されたベニグノ(ニノイ)アキノ上院議員)の妻)の下で、1987年に新たな憲法が作られます。この憲法は、独裁政権の再来阻止を念頭に置いて、大統領の再選禁止を規定した他、地方自治の保障(第2条第25節)や地方自治法の制定(第10条第3節)を規定しました。この憲法を受けて1991年に地方自治法(The Local Government Code of 1991)が作られます。この地方自治法では、地方開発計画の企画立案・実施権限をはじめとして地方政府に大きな権限が与えられます。例えば、同法第129節は、地方政府は自らの歳入源(税金や課金)を創設する力を有すると規定し、課税権を地方政府に与えています。
このように、紙の上では、1987年憲法と1991年地方自治法によって地方分権が高らかに謳われることになったのですが、実際には、地方分権はさほど進みませんでした。それは、地方分権を進める資金がそもそも不足していましたし、地方政府の多くはその歳入を国から配分される内国歳入割当金(IRA)に依存しており(州及び町の約7割~8割、市の歳入の5割程度)、その結果、中央政府が地方政府に影響力を行使できる状況となっていたためです。
この状況が変化するきっかけとなったのが、「マンダナスーガルシア事案」に関する2019年4月の最高裁判決です。「マンダナス-ガルシア事案」は、2つの訴訟をまとめた呼称ですが、いずれの訴訟も、中央政府が地方政府に公正な割合の資金を与えることを求めていました。最高裁は、地方自治法第284節の「内国歳入の割当て」という用語は憲法違反であり、「内国歳入」という用語を削除することを中央政府に求めるとの判断を示しました。この結果、中央政府が地方政府に割り当てるのは内国歳入だけではなく、すべての国家歳入となりました。これは、地方政府の財源増大(内国歳入割当金では37.89%の増加)及び権限の拡大と、その裏返しとしての中央政府の財源及び権限の縮小を生みます。
2021年6月、ドゥテルテ大統領は、「マンダナス-ガルシア事案」の最高裁判決を受けて、行政命令第138号を発出します。これは、中央政府14省庁等から地方政府に対して66の機能を完全に分権することを命令したものです。代表的なものとして、農業サービス(農業省)、地方インフラサービス(教育省)、天然資源管理サービス(環境天然資源省)、歳入運用機能(財務省)、保健機能(保健省)、法と秩序の維持(内務自治省)、雇用促進(労働雇用省)、地方インフラサービス(公共事業道路省)、住宅サービス(国家住宅庁)が挙げられます。この大幅な地方分権が、2022年から2024年まで進められています。(なお、この終了時期は、マルコス新大統領によって2027年まで延期されました。)
日本においても、1993年から第一次地方分権改革が行われ、1999年には地方分権一括法が施行され、機関委任事務が廃止されました。また、2006年からの第二次地方分権改革では、地方分権改革推進法(2010年までの時限法)の下で、地方からの提案を国が検討し、既存の規則の変更を図る提案募集方式が導入され、また、地方に対する義務が一層緩和されました。この一連の改革は、「地方にできることは地方に委ねる」という原則に基づいています。この原則に反対する人はそれほど多くないでしょう。
一方で、日本では、地方分権のデメリットとして、(1)地域間格差が拡大するおそれがある、(2)地方自治体の持つ力が大きくなり過ぎるということが指摘されていました。日本では、前者については、地域間の経済的格差を補うために地方交付税があり、集められた財源が財政力の弱い地方自治体に再配分されることになっています。後者については、例えば、地方自治体が条例によって地方税の税目を新設する場合(法定外税)、それまでの許可制は改められたものの、総務大臣に対して協議しなければならず、そのプロセスの中で、財務大臣が異議を、地方財政審議会が意見を総務大臣に伝えることができ、それを踏まえた上で、総務大臣が同意を与えるかどうかを決めることができるようになっており、中央の統制は引き続き保たれています。また、そもそも、法定外税の納税額が、全納税者の納税額の10分の1を継続に超えると見込まれる特定納税義務者がいる場合には、地方自治体は、上記プロセスに先立ち、その者から意見を聴取しなければなりません。
特に、地方税の創設について、フィリピンにおいては、日本のような歯止めがあるかないかについては、まだ十分に調査ができていないのですが、仮に歯止めがない場合には、地方政府がさほど制約なく地方税を創設できることになり、日本を含む外国から投資している企業にとっては、思いがけない負担が付加される可能性もあるのではないかと思います。
以上をまとめますと、1987年憲法から約25年の時間差をもって「行きすぎた地方分権」が現出する可能性があるのではないかというのが最近感じ始めていることです。これを明確に理解するには、かなり専門的な知識を要求されますので、専門家の方々から忌憚のないご意見を賜れば幸いです。
このように、紙の上では、1987年憲法と1991年地方自治法によって地方分権が高らかに謳われることになったのですが、実際には、地方分権はさほど進みませんでした。それは、地方分権を進める資金がそもそも不足していましたし、地方政府の多くはその歳入を国から配分される内国歳入割当金(IRA)に依存しており(州及び町の約7割~8割、市の歳入の5割程度)、その結果、中央政府が地方政府に影響力を行使できる状況となっていたためです。
この状況が変化するきっかけとなったのが、「マンダナスーガルシア事案」に関する2019年4月の最高裁判決です。「マンダナス-ガルシア事案」は、2つの訴訟をまとめた呼称ですが、いずれの訴訟も、中央政府が地方政府に公正な割合の資金を与えることを求めていました。最高裁は、地方自治法第284節の「内国歳入の割当て」という用語は憲法違反であり、「内国歳入」という用語を削除することを中央政府に求めるとの判断を示しました。この結果、中央政府が地方政府に割り当てるのは内国歳入だけではなく、すべての国家歳入となりました。これは、地方政府の財源増大(内国歳入割当金では37.89%の増加)及び権限の拡大と、その裏返しとしての中央政府の財源及び権限の縮小を生みます。
2021年6月、ドゥテルテ大統領は、「マンダナス-ガルシア事案」の最高裁判決を受けて、行政命令第138号を発出します。これは、中央政府14省庁等から地方政府に対して66の機能を完全に分権することを命令したものです。代表的なものとして、農業サービス(農業省)、地方インフラサービス(教育省)、天然資源管理サービス(環境天然資源省)、歳入運用機能(財務省)、保健機能(保健省)、法と秩序の維持(内務自治省)、雇用促進(労働雇用省)、地方インフラサービス(公共事業道路省)、住宅サービス(国家住宅庁)が挙げられます。この大幅な地方分権が、2022年から2024年まで進められています。(なお、この終了時期は、マルコス新大統領によって2027年まで延期されました。)
日本においても、1993年から第一次地方分権改革が行われ、1999年には地方分権一括法が施行され、機関委任事務が廃止されました。また、2006年からの第二次地方分権改革では、地方分権改革推進法(2010年までの時限法)の下で、地方からの提案を国が検討し、既存の規則の変更を図る提案募集方式が導入され、また、地方に対する義務が一層緩和されました。この一連の改革は、「地方にできることは地方に委ねる」という原則に基づいています。この原則に反対する人はそれほど多くないでしょう。
一方で、日本では、地方分権のデメリットとして、(1)地域間格差が拡大するおそれがある、(2)地方自治体の持つ力が大きくなり過ぎるということが指摘されていました。日本では、前者については、地域間の経済的格差を補うために地方交付税があり、集められた財源が財政力の弱い地方自治体に再配分されることになっています。後者については、例えば、地方自治体が条例によって地方税の税目を新設する場合(法定外税)、それまでの許可制は改められたものの、総務大臣に対して協議しなければならず、そのプロセスの中で、財務大臣が異議を、地方財政審議会が意見を総務大臣に伝えることができ、それを踏まえた上で、総務大臣が同意を与えるかどうかを決めることができるようになっており、中央の統制は引き続き保たれています。また、そもそも、法定外税の納税額が、全納税者の納税額の10分の1を継続に超えると見込まれる特定納税義務者がいる場合には、地方自治体は、上記プロセスに先立ち、その者から意見を聴取しなければなりません。
特に、地方税の創設について、フィリピンにおいては、日本のような歯止めがあるかないかについては、まだ十分に調査ができていないのですが、仮に歯止めがない場合には、地方政府がさほど制約なく地方税を創設できることになり、日本を含む外国から投資している企業にとっては、思いがけない負担が付加される可能性もあるのではないかと思います。
以上をまとめますと、1987年憲法から約25年の時間差をもって「行きすぎた地方分権」が現出する可能性があるのではないかというのが最近感じ始めていることです。これを明確に理解するには、かなり専門的な知識を要求されますので、専門家の方々から忌憚のないご意見を賜れば幸いです。
在セブ総領事 山地秀樹
(参考文献)
“the Devolution of National Agency and Its Implications to LGU-GENSAN” September 2021 E-Bulletin #29”, Zedrick Albert F. Guanzon & Michael E. Peligro, Human Resource Management & Development Office, General Santos City
https://gensanhrmdo.org/home/the-devolution-of-national-agency-and-its-implications-to-gensan-hrmdo-september-2021-e-bulletin-29/
Executive Order No.138 by the President of the Philippines
“Full Devolution of Certain Functions of the Executive Branch to Local Governments, Creation of a Committee on Devolution, and for Other Purposes”
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210601-EO-138-RRD.pdf
Frequently Asked Questions – Mandanas-Garcia SC Ruling
As of November 9, 2021
https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/Mandanas-Garcia-Case/IEC-Materials/FAQs-Mandanas-Garcia-Ruling.pdf
(了)