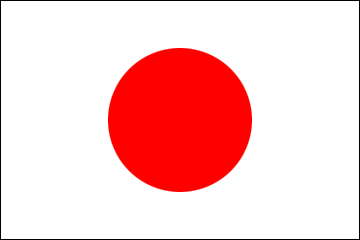セブ便り(第17回) 「フィリピンのゴミ問題と廃プラスチック・リサイクル企業「グーン」」
令和5年4月12日
セブ便り(第17回)「フィリピンのゴミ問題と廃プラスチック・リサイクル企業「グーン」」
フィリピンのゴミ問題については、ずいぶん前から関心を有していました。フィリピンの都市郊外にスモーキー・マウンテンと呼ばれるゴミの山が拡がっており、そこにゴミ拾いにくるスカベンジャーと呼ばれる少年少女の貧しい生活をあるTV番組が特集していたのを20代の時に視聴したのがきっかけだったと思います。「あの子らが衛生的で健康的な生活を送れるようにならないだろうか。」セブに来てからもこの問題意識を持ち続けていました。
幸い、オープン・ダンピング・サイトと呼ばれるゴミの山は、数年前に法律で禁止となり、土砂をかぶせて「衛生埋立処分場」に変わっていました。着任1カ月後、マンダウエ市のウマパッドにある衛生埋立処分場を視察しました。
幸い、オープン・ダンピング・サイトと呼ばれるゴミの山は、数年前に法律で禁止となり、土砂をかぶせて「衛生埋立処分場」に変わっていました。着任1カ月後、マンダウエ市のウマパッドにある衛生埋立処分場を視察しました。
(ウマパッド衛生埋立処分場 黒いパイプはメタンガス排出用)

(マンダウエ市職員及び環境天然資源省職員とともに 2022年6月10日)


(マンダウエ市職員及び環境天然資源省職員とともに 2022年6月10日)

ウマパッドに行く前に、ジョナス・コルテス・マンダウエ市長から、「ゴミ処分場を単に埋め立てても、メタンガスは出るし、汚染された地下水が海に流れ込むため環境には良くない。しかし、フィリピンの議会では、焼却炉の建設に反対する環境保護グループの力が強く、ゴミの焼却処分が難しい。」との説明を受けました。
その後ほどなくして、勇気づけられる情報を得ました。セブ市の北、コンソラシオン市に「グーン」という廃プラスチック・リサイクル企業があります。本社は横浜にあり、コンソラシオン市の企業はそのフィリピン支店です。主な事業は、(1)廃プラスチックなどからフラフと呼ばれる燃料を製造すること(このフラフは、石炭と同等の火力を発生しますが、二酸化炭素排出量は17%も低いそうです。)、(2)木くずの廃材からバイオマス発電に用いるチップを製造すること、(3)ゴミ処理のコンサルティングです。
「グーン」は、2012年以降、JICAや横浜市などの支援を受けてセブでの事業化調査をした後、2017年7月から当地で事業を始めました。現在の同企業の廃プラスチック処理能力は、一日当たり50トンから75トンだということで、メトロセブの廃プラスチック排出量が一日当たり220トンということですから、その3分の1をカバーできる能力があるそうです。
同社は、セブ市北隣にあるマンダウエ市の廃プラスチック処理を5年間継続してきています。2018年頃は、マンダウエ市から運び込まれるゴミのうち廃プラスチックとして使えるのは持ち込まれるゴミの65%程度だったそうですが、バランガイと呼ばれる自治地区に対してゴミの分別をマンダウエ市や横浜市が啓発した結果、現在はその割合が85%にまで向上したということです。廃プラスチックを処理することによって、処分場に持って行くゴミの量は、以前の量の40%から45%にまで削減できているようです。グーン社は、コンソラシオン市の北側にあるダナオ市とも新たな契約を結んだとのことでした。セブで活動する日本企業が、セブのゴミ埋設量の削減に貢献し、ひいては地球環境を含めた環境問題に貢献していることを、同じ日本人として誇りに思います。
その後ほどなくして、勇気づけられる情報を得ました。セブ市の北、コンソラシオン市に「グーン」という廃プラスチック・リサイクル企業があります。本社は横浜にあり、コンソラシオン市の企業はそのフィリピン支店です。主な事業は、(1)廃プラスチックなどからフラフと呼ばれる燃料を製造すること(このフラフは、石炭と同等の火力を発生しますが、二酸化炭素排出量は17%も低いそうです。)、(2)木くずの廃材からバイオマス発電に用いるチップを製造すること、(3)ゴミ処理のコンサルティングです。
「グーン」は、2012年以降、JICAや横浜市などの支援を受けてセブでの事業化調査をした後、2017年7月から当地で事業を始めました。現在の同企業の廃プラスチック処理能力は、一日当たり50トンから75トンだということで、メトロセブの廃プラスチック排出量が一日当たり220トンということですから、その3分の1をカバーできる能力があるそうです。
同社は、セブ市北隣にあるマンダウエ市の廃プラスチック処理を5年間継続してきています。2018年頃は、マンダウエ市から運び込まれるゴミのうち廃プラスチックとして使えるのは持ち込まれるゴミの65%程度だったそうですが、バランガイと呼ばれる自治地区に対してゴミの分別をマンダウエ市や横浜市が啓発した結果、現在はその割合が85%にまで向上したということです。廃プラスチックを処理することによって、処分場に持って行くゴミの量は、以前の量の40%から45%にまで削減できているようです。グーン社は、コンソラシオン市の北側にあるダナオ市とも新たな契約を結んだとのことでした。セブで活動する日本企業が、セブのゴミ埋設量の削減に貢献し、ひいては地球環境を含めた環境問題に貢献していることを、同じ日本人として誇りに思います。
(グーン社フィリピン支店の小西支店長と原木副支店長とともに)

「グーン」による取組がフィリピン国内に拡がっていけばいいなとは思いますが、もちろん、一企業の取組みと国家レベルの動きを同一線上で論ずることはできません。これまで調べた限りでは、私は、フィリピンが日本のように焼却炉を導入してゴミを10分の1以下に減容し、その上で、3R(Reduce, Reuse, Recycle)を適切に実施して、循環型の社会を形成していくことには楽観的ではありません。
第1の理由は、ゴミの焼却処分に反対する環境保護団体の存在です。環境保護派の方とも話をしましたが、「ゴミの焼却処分はいけない。ダイオキシンが発生する。それを証拠づけるデータがある。」の一点張りです。日本の場合、1999年に「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、対策技術が開発されたため、2011年のゴミ焼却施設からのダイオキシン類排出量は1997年に比べ約99%減少したわけですが、環境保護派が、2011年より前のデータを用いれば、「焼却処分は環境に悪い」と主張を容易に展開できるわけです。なお、ゴミの分別が重視される大きな理由は、焼却効率を上げるためですから、焼却処分を否定してしまえば、ゴミの分別の重要性も落ちてしまいます。
第2の理由は、環境保護派の主張を助長する環境関連法令です。代表的な環境関連法令は、1999年大気浄化法、2001年固形廃棄物管理法、そして、2022年拡大生産者責任法です。大気浄化法については、制定直後は、ゴミの焼却処分を実質的に禁止したものと解されていました。2002年1月に最高裁により、同法は、「廃棄物の焼却処分を完全に禁止したものではなく、毒性のあるガスの排出を禁止したにすぎない。」と判断されましたが、2013年に同最高裁判決に沿って改正案が提案されたものの、反対が多く、改正には至りませんでした。
固形廃棄物管理法は、そもそもゴミ焼却を行わない前提で策定された法律で、3Rが理想通りに行われることを前提としています。環境保護派は、この法律を厳格に実行できればゴミの排出量はゼロになり、焼却処分も不要であると主張します。環境保護派が見落としているのは、国民からの3Rへの協力の程度です。現実には、フィリピンは、毎年年間約1600万トンのゴミを排出し、その多くは、国内に約900ある処分場に捨てられているのです。
更に、上記の法及び拡大生産者責任法では、住民や消費者の責務及びそれらの協力義務が一切規定されていません。これは日本の環境関連法令との大きな違いです。例えば、日本の容器包装リサイクル法(1995年制定)は、拡大生産者責任の考えに基づいて導入された法律ですが、消費者の役割(分別排出)、市町村の役割(分別収集)、事業者の役割(リサイクル)が明記され、三者が一体となって、容器包装リサイクルに取り組むことになっています。一方、フィリピンでの2022年拡大生産者責任法では、事業者の責任のみに焦点が当てられており、罰則も事業者に対してのみ設けられています。加えて、この法律を元に2028年までに80%の自社ブランドのプラスチック容器等を回収することが義務づけられています。消費者や地方政府が本来の役割を果たさずに、事業者にのみ回収義務を押しつければ、事業者にとっては過大な負担となるでしょう。
第3の理由は、セブ便り16でも述べた地方分権の動きです。ゴミ焼却炉については高度な専門性が必要です。このような専門家は中央政府で働いています。地方分権の名の下に、これらの専門家、テクノクラートを他の省に異動させたり、退職させるのは得策とは言えません。
また、このような施設の整備には、一時的に多大な費用が必要です。国からの補助金は欠かせません。日本でも、ゴミ処理施設の処理能力は、1975年から2000年にかけて、日量約11万トンから日量約20万トンに拡大しましたが、この期間に、ゴミ処理施設国庫補助金は約220億円から約1600億円に拡大しています。膨大な予算をもって国が関与しなければ国家レベルでのゴミ処理は進展しません。
現在、いくつかの廃棄物利用発電(WTE)事業が外国の企業から提案を受けて地方政府レベルで検討されていますが、これも、中央政府からの緊密な関与がなく、地方政府の側に高度の専門的知見を有する人材がいなければ、当初の計画通りに円滑には進まないかもしれません。
以上の指摘は、フィリピン政府の政策を批判するものではありません。フィリピンには、フィリピンの実情に即したやり方があるのかもしれません。しかし、国民の税金を多く投入している割に、ゴミ処理の効果が上がっていないと感じられる時には、国の責務や国民の責務にもう少し目を向けていただければ有り難いと思います。
フィリピンのゴミ問題を解決するために、日本政府はできる限り支援してきました。しかし、ゴミ問題に関しての支援は、個々のプロジェクト実施や技術協力といったレベルにとどまるのではなく、法令や制度といった国の設計図についても視野に入れる必要があるように思われます。
第1の理由は、ゴミの焼却処分に反対する環境保護団体の存在です。環境保護派の方とも話をしましたが、「ゴミの焼却処分はいけない。ダイオキシンが発生する。それを証拠づけるデータがある。」の一点張りです。日本の場合、1999年に「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、対策技術が開発されたため、2011年のゴミ焼却施設からのダイオキシン類排出量は1997年に比べ約99%減少したわけですが、環境保護派が、2011年より前のデータを用いれば、「焼却処分は環境に悪い」と主張を容易に展開できるわけです。なお、ゴミの分別が重視される大きな理由は、焼却効率を上げるためですから、焼却処分を否定してしまえば、ゴミの分別の重要性も落ちてしまいます。
第2の理由は、環境保護派の主張を助長する環境関連法令です。代表的な環境関連法令は、1999年大気浄化法、2001年固形廃棄物管理法、そして、2022年拡大生産者責任法です。大気浄化法については、制定直後は、ゴミの焼却処分を実質的に禁止したものと解されていました。2002年1月に最高裁により、同法は、「廃棄物の焼却処分を完全に禁止したものではなく、毒性のあるガスの排出を禁止したにすぎない。」と判断されましたが、2013年に同最高裁判決に沿って改正案が提案されたものの、反対が多く、改正には至りませんでした。
固形廃棄物管理法は、そもそもゴミ焼却を行わない前提で策定された法律で、3Rが理想通りに行われることを前提としています。環境保護派は、この法律を厳格に実行できればゴミの排出量はゼロになり、焼却処分も不要であると主張します。環境保護派が見落としているのは、国民からの3Rへの協力の程度です。現実には、フィリピンは、毎年年間約1600万トンのゴミを排出し、その多くは、国内に約900ある処分場に捨てられているのです。
更に、上記の法及び拡大生産者責任法では、住民や消費者の責務及びそれらの協力義務が一切規定されていません。これは日本の環境関連法令との大きな違いです。例えば、日本の容器包装リサイクル法(1995年制定)は、拡大生産者責任の考えに基づいて導入された法律ですが、消費者の役割(分別排出)、市町村の役割(分別収集)、事業者の役割(リサイクル)が明記され、三者が一体となって、容器包装リサイクルに取り組むことになっています。一方、フィリピンでの2022年拡大生産者責任法では、事業者の責任のみに焦点が当てられており、罰則も事業者に対してのみ設けられています。加えて、この法律を元に2028年までに80%の自社ブランドのプラスチック容器等を回収することが義務づけられています。消費者や地方政府が本来の役割を果たさずに、事業者にのみ回収義務を押しつければ、事業者にとっては過大な負担となるでしょう。
第3の理由は、セブ便り16でも述べた地方分権の動きです。ゴミ焼却炉については高度な専門性が必要です。このような専門家は中央政府で働いています。地方分権の名の下に、これらの専門家、テクノクラートを他の省に異動させたり、退職させるのは得策とは言えません。
また、このような施設の整備には、一時的に多大な費用が必要です。国からの補助金は欠かせません。日本でも、ゴミ処理施設の処理能力は、1975年から2000年にかけて、日量約11万トンから日量約20万トンに拡大しましたが、この期間に、ゴミ処理施設国庫補助金は約220億円から約1600億円に拡大しています。膨大な予算をもって国が関与しなければ国家レベルでのゴミ処理は進展しません。
現在、いくつかの廃棄物利用発電(WTE)事業が外国の企業から提案を受けて地方政府レベルで検討されていますが、これも、中央政府からの緊密な関与がなく、地方政府の側に高度の専門的知見を有する人材がいなければ、当初の計画通りに円滑には進まないかもしれません。
以上の指摘は、フィリピン政府の政策を批判するものではありません。フィリピンには、フィリピンの実情に即したやり方があるのかもしれません。しかし、国民の税金を多く投入している割に、ゴミ処理の効果が上がっていないと感じられる時には、国の責務や国民の責務にもう少し目を向けていただければ有り難いと思います。
フィリピンのゴミ問題を解決するために、日本政府はできる限り支援してきました。しかし、ゴミ問題に関しての支援は、個々のプロジェクト実施や技術協力といったレベルにとどまるのではなく、法令や制度といった国の設計図についても視野に入れる必要があるように思われます。
在セブ総領事 山地秀樹
(参考文献)
「日本の廃棄物処理の歴史と現状」、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 2014年2月
https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf
大気浄化法 (Clean Air Act of 1999, RA8479)
https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2015/09/RA-8749.pdf
固形廃棄物管理法 (Ecological Solid Waste Management Act 2001, RA9003)
https://www.officialgazette.gov.ph/2001/01/26/republic-act-no-9003-s-2001/
拡大製造者責任法 (Extended Producer Responsibility Act of 2022, RA11898)
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2022/ra_11898_2022.html
(了)