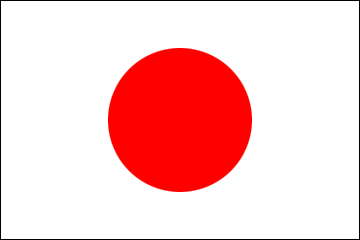セブ便り(第22回)セブでの日本武道
令和5年9月22日
セブ便り(第22回)「セブでの日本武道」
6月から8月にかけて、セブで活動している日本武道のクラブを訪問する機会を得ました。セブ盆栽協会の友人から、セブには、剣道、柔道、合気道、空手といった日本武道のクラブがあることを教えてもらいました。私は、フィリピンの人々が、何故日本武道に興味をもったのか、そして日本武道から何を学んでいるのかに関心がありましたので、それぞれのクラブを訪問してそれらを探ってみることにしました。
(セブ剣道クラブ)


どのクラブも、大体15名から20名くらいのメンバーで構成されています。1、2名の日本人を除き、ほとんどがフィリピン人です。練習は、公共のスポーツホールやホテル内のジムの一角を週に数回、数時間借りて行われていました。どの「道場」に入っても、日本武道特有のピーンと張り詰めた雰囲気があります。私は、子供の頃剣道をやっていましたので、この雰囲気をとても懐かしく感じました。
(中央ビサヤ柔道協会)

日本武道のクラブを訪問してすぐに、私は、セブ独特(フィリピン独特と言ってもいいかもしれませんが)の特徴に気がつきました。まず驚いたのは、クラブメンバーの多様性です。日本では、男子と女子を別々にして、または、熟練度によってクラス分けして、練習する傾向がありますが、これらのクラブでは、文字通り老若男女が一緒になって練習しています。この多様性は賞賛に値するものだと思いました。
(シティ合気道セブ)

次に、クラブ内のどのメンバーも練習で置き去りにせず、手助けしてあげる雰囲気がどのクラブにもあることに感銘を受けました。経験のあるメンバーや年配のメンバーが、初心者や少年少女を機会ある毎に手助けしてあげています。メンバーの誰もが、誰一人として取り残されず、楽しく練習を続けられることに意を用いているようでした。日本では、それぞれのメンバーが自らの技量の向上に懸命になるあまり、他のメンバーのことにはあまり関心を払わない傾向があるように思えますが、セブではそのようなことはありませんでした。これは両国の大きな違いです。各クラブでみられた包摂性の意識は、本当に素晴らしいことであると思いました。
(中央ビサヤ空手協会セブ)

上記の多様性と包摂性は、練習のスペースや時間が制約されているとの事情からくるものもあるでしょう。しかし、他者の面倒をよくみる優しい心根をもつフィリピン人の特性が最も大きな要素となっているように思えるのです。
(柔道の練習風景)

何人かの方々に、何故日本武道を始めたのかを尋ねてみました。ある方は、日本文化への一般的な興味が日本武道を始めた原動力になっていると答えました。別の方は、両親の勧めで日本武道を始めたということでした。最も興味深かったのは、ハリウッド映画の影響です。剣道クラブのメンバーの一人は、トム・クルーズ主演の「ラスト・サムライ」を観て、剣道を始めようと思ったと述べていました。合気道クラブの何人かのメンバーは、スティーブン・セガール主演の「アウト・フォー・ジャスティス(1991年)」や「沈黙の戦艦(1992年)」で、セガールが合気道の技術を存分に発揮するのをみて、「自分も合気道をやってみたい。」と思ったということでした。
(合気道の練習風景)


「日本武道から何を学んだか。」という質問もしてみました。多くの方々がそれぞれの武道の教えや目標から学ぶところが大であったと述べていました。例えば、柔道ならば、「精力善用」や「自他共栄」ですし、剣道であれば、「剣の理法の修練による人間形成」です。合気道の場合は、他者といたずらに優劣を競うのではなく、稽古を積み重ねて心身の錬成を図ること、そして、お互いを尊重する和合の精神を学んだとのことでした。そして、これらの教えや目標は、日常生活や自らの職業にも応用できているとのことでした。
最後に、セブ市のいくつかの小学校で導入されているスポーツ・プログラムを紹介したいと思います。セブ市のティサ第2小学校は、教育省のセブ市部局により進められている「スポーツ・プログラム校」に指定されています。そのプログラムの一つとして空手のレッスンを週に数回行っています。このプログラムは、フィリピンの小学生レベルで様々なスポーツの普及を目指すもので、空手以外にも、フィリピンの武道であるアーニス、チェス、体操、卓球、テコンドー、バレーボール、カンフー(ウーシュー)が授業に取り入れられているそうです。
セブ市の別の小学校では、柔道をスポーツの授業に取り入れることを検討しているそうです。このような動きによって、日本武道の裾野が更に広がればよいなと考えています。
(空手の練習風景)


在セブ総領事 山地秀樹
(了)